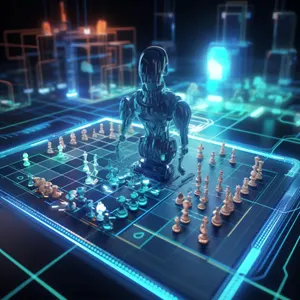AI投資ツールには「機械学習」の機能があると言われます。機械学習とは、膨大なデータから役に立つ法則性や判断基準を学び、未知の状況に対する予測を行うAI技術です。以前から、株価の値動きや各企業の業績などの膨大なデータを機械学習させ、その能力を活用すれば、より安全に顧客資産を運用できると考えらていましたが、その仮説の正しさを裏付ける事例が出始めています。
ディープラーニング(深層学習)
さらに、最新のAI投資ツールは、機械学習の発展形となる「ディープ・ラーニング(深層学習)」の能力を備えていることを謳っています。ディープ・ラーニングとは、人間の脳神経をまねたコンピューターが自ら何を基準に判断するかも決め、人間の指示を待たずに独自に学習を発展させる技術です。
人間には真似できない技

最新のAI投資ツールの人工知能は、常に膨大な株取引や企業の財務などのデータを収集しているようです。数千社以上の決算資料を一度に読み、何が起きているかをリアルタイムで分析しているといいます。
SNSと株価の関係
さらに、マクロ経済や政治などのニュースと、個別銘柄の相関関係も把握しています。SNSの投稿など、社会のトレンドを掴むための情報も蓄積されています。そのうえで、「短期間の株価高騰」が期待できる株を抽出します。これらは人間には決して真似できない高度で複雑な行為です。
<AI Refereeのポイント(公式サイトより)>
| 1 |
AIによる膨大なデータ解析 |
| 2 |
投資効率最大3倍増 |
| 3 |
利用者満足度97.8% |
機関投資家の進化
21世紀に入ってから、機関投資家や欧米のファンドの間ではAIの活用が当たり前になりました。とりわけヘッジファンドは、超高度な統計学や数学を覚えた最先端AIを駆使して相場に臨んでいます。さらに彼らは、リスクに対してどれだけの収益を上げたかを数値化した「シャープレシオ」に基づき、運用成績の悪いAIを排除します。競争によって絶えずAIの頭脳とアルゴリズムを進化させています。
個人が負ける理由
AIを駆使するプロの投資会社に対して、素人の個人投資家が立ち向かうのは至難の業です。
とくに株の初心者は、その売買の手の内や心理状況を、AIに見透かされています。
「このようなニュースが流れたとき、個人投資家はこういう行動に出る」というパターンを、AIは熟知しているのです。
個人投資家が機関投資家の「食い物」にされるのは、このためです。
初の「一般」向け株投資AI
今や個人投資家もAIを活用しなければ、機関投資家に負け続けることになります。
とはいえ、個人投資家には自らAIを開発する資金力はありません。
そのような背景の中で誕生したのが、汎用型AI投資ツールです。
<汎用型AI投資ツールの特徴>
| 歴史的な位置づけ |
一般投資家がAIを活用する先駆的な事例 |
| 開発指向 |
オープン型・クラウド型・フィードバック型 |
| サービス形態 |
多人数が利用 |
| 能力 |
自己学習、リスク管理 |
| アップデート頻度 |
必要に応じて随時 |
ファンドマネジャーの運用方法を学習
汎用型AI投資ツールの開発には、長い歴史があります。まず、過去のロボット研究の成果と知恵をふまえ、プロトタイプが制作されました。そのうえで、トップクラスのファンドマネジャーの運用方法を学習させました。相場での訓練に数年以上が費やされたといいます。資料によると、株価予測にとどまらず、相場全体の下落リスクなどに関する管理能力も付与されました。
新しいAIが勝つ
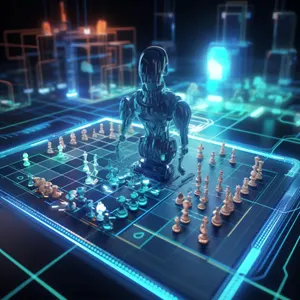
株投資の世界では、AI対AIの戦いになったとき、能力の高いAIが勝つのが常識です。
最先端の技術やデータ分析力を備えた人工知能に軍配が上がるのです。
一人勝ちを謳歌していた最先端AIも、時間の経過とともに時代遅れになり、他のAIに完敗することがよくあります。
AI Refereeは、最新の人工知能の技術が取り入れられいるそうで、古いシステムよりも優位性がある可能性があります。会社規模が小さいため、「オープン型・クラウド型」のシステムとなっていると想定され、技術的なアップデートの頻度が高いと考えられます。
精度が向上し続ける
従来、投資用のAIツールは特定の企業だけに限定して使われてきました。
開発陣営も、大手システム会社だけがナレッジを独占する「クローズド型」でした。
これに対して、AI Refereeはオープン型であるため、幅広い会員に使われています。
利用者から常により多くのフィードバックが得られ、かつ、その知見は多くの開発者の間で共有されます。
その結果、AIの精度やノウハウが向上しやすくなっています。
コストを多人数でシェア
汎用型AI投資ツールは、開発費やランニングコストを多数のユーザーでシェアする形になっているのも特徴です。
結果的に、利用者一人一人の経済的な負担が少なくなります。
開発側としても、費用の回収が容易であるだけでなく、永続的に機能向上に取り組みやすい仕組みになっているのです。